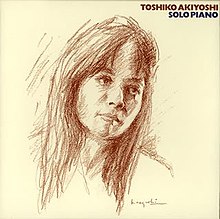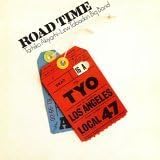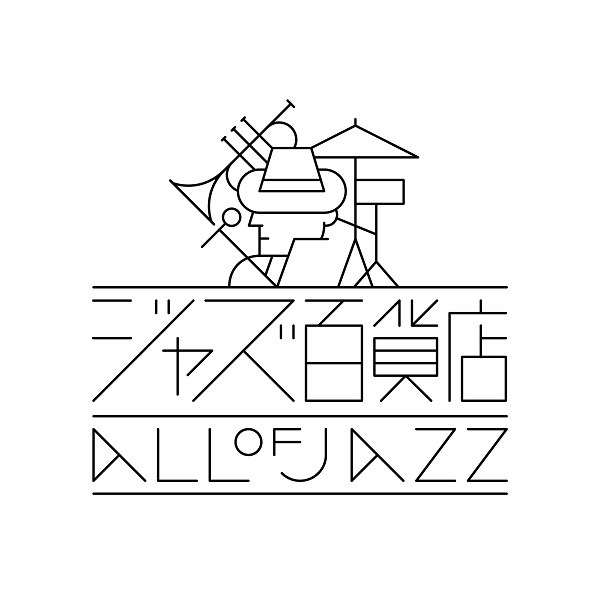Toshiko Akiyoshi リーダー作③1970~1976年
ルー・タバキンと再婚し、大阪万博のために再来日します。その後、拠点をロスに移すとともに、念願であっトシコ=タバキン・ビッグ・バンドを結成します。「孤軍」など和のテイストを強く取り入れた作品を作るようになったのもこの時期です。
・新宿ジャズ談義の会 :穐吉敏子 CDレビュー 目次
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作①1953-1958
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作②1960-1968
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作③1970-1976・・・このページ
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作④1976-1979
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作⑤1980-1987
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作⑥1990-1996
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作⑦1997-2005
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作⑥2006-2018
TOSHIKO AKIYOSHI IN JAPAN / 秋吉敏子
秋吉敏子(p), Lew Tabackin(ts,fl), Bob Daugherty(b), Mickey Roker(ds)
大阪万博・EXPO’70での秋吉カルテットの公演記録
ルー・タバキン入りのワンホーンカルテットの初作で日本の万博、EXPO’70での公演の記録。冒頭曲①オパス・ナンバー・ゼロ、から秋吉は気合いの入った激しいソロを聞かせ、タバキンもこれに応えていいテナーを聞かせる。タバキンのテナーの音色と奏法は「トップ・オブ・ザ・ゲート」のジョーヘン的なものから私好みのロリンズ的なものに多少変わり、当時の日本で受け入れやすいものになったと思う(私自身、近年、やっとジョーヘンが受け入れられるようになった。タバキンはこの後、ビッグバンド期に入るとエディ・ロックジョー・デイビス化して、私はまた苦手になってしまう。)。③ロング・イエロー・ロード、は18分近い超大作となって再演され、ビッグバンド時代の重要曲となる予告になっている。最初から同曲とわからないアブストラクトなテナーとピアノのアドリブが延々と続き、最後の1分だけメロディが出てくるという構成になっている。タバキンのフルートは当初から幽玄な日本の笛のような音色で、秋吉の音楽に合っている。(hand)
JAZZ, THE PERSONAL DIMENSION(LP) / 秋吉敏子
1971.2.5
日Victor

おすすめ度
hand ★★★★
秋吉敏子(p), Lew Tabackin(ts,fl), Lyn Christie(b), Bill Goodwin(ds)
CD化が望まれるカーネギーホールでのライブ録音
未CD化3部作とでも言いたくなる不幸な3枚がここから続く。単体CD3枚化が理想だが2枚組でもいいので、フレッシュサウンドか、近年、秋吉の新旧録音をCD化しているスタジオソングスからCD化してほしい。この盤は、8年ぶりの米国録音で、カーネギーホールでのライブ録音。①ザ・ヴィレッジ、はこれまで木更津甚句、とされていた曲が秋吉のオリジナル曲、として初めてソロ演奏され、素晴らしい内容。他の3曲はルー・タバキンの入ったカルテット演奏。②春の海、はフルート入りで、和のテイストを強く感じる激しい演奏で好感だ。③④はテナー。③ラバーマン、のタバキンはこれまでのスタイルからズートまでは行かないがさらに滑らかとなっている。と思うと④ステート・オブ・ビーイング、では実験色の濃い演奏で、コルトレーンを感じる部分もある。最後はロング・イエロー・ロードのメロディで終わる。(hand)
MEDITATION(LP) / 秋吉敏子
1971.2.23 & 26
Dan

おすすめ度
hand ★★★★
秋吉敏子(p), Lew Tabackin(ts,fl), Lyn Christie(b), Albert Heath(ds)
スタンダードやボサもあるカルテットの演奏
この盤には秋吉のピアノ演奏ジャケと夕陽?ジャケの2種類があり、どちらもダン・レーベルだが、曲順も冒頭曲とラスト曲が入れ替わっている。私の所有盤は、ピアノ演奏ジャケ盤。こちらが初盤だと思う。①ホワット・ナウ・マイ・ラブ、は秋吉には珍しいラブソングをラブソングらしく演奏したもの。真面目な秋吉は、深刻で精神性や民族を感じる演奏が多いので意外な感じがした。②星影のステラ、もスタンダードでタバキンのテナーはロリンズ的なスタイルになっている。コルトレーン派テナーは多数いて、ロリンズ派はいないと言われているが、この時期のタバキンはロリンズ派に聞こえる。③柳よ泣いておくれ、はフルートで、④ストレート・ノー・チェイサー、はテナーだ。ラスト⑤メディテーション、は真面目な秋吉にジョビンのボサを想定できず、タイトルからオリジナルかと思って聞くと、ジョビン曲がフルートで軽快に演奏される。これを売れると考え、再発時に、この曲を冒頭にジャケも変えたのだと想像するが、他の曲と秋吉もタバキンもイメージが違うので、オマケ的に入っていたほうが違和感がないと思う。夕陽ジャケは軽快ではなくスピリチュアルな感じに見えてしまっている。(hand)
SUMIE(LP)←The Personal Aspect In Jazz(4channel LP) / 秋吉敏子
1971.3.4
日Victor


おすすめ度
hand ★★★★★
しげどん ★★★☆
ショーン ★★★★
秋吉敏子(p), Lew Tabackin(ts,fl), Lyn Christie(b), Albert Heath(ds)
CD化が切望される和のテイストが自然な盤
元盤は当時流行しそうであった4チャンネル用LPで、タイトルは「ザ・パーソナル・アスペクト・イン・ジャズ」(1971年)で、秋吉の演奏姿ジャケ。4チャンネル専用プレーヤーでしかかからないレコードであったため、4チャンネルの衰退とともに聞けない盤となっていた。これを通常のステレオ盤LPとして77年に再発売したのが「すみ絵」でジャケはローマ字でSumieの文字。8年後の79年に発売の「すみ絵」とは、日本文字は同じだがローマ字が異なり、こちらがSumieで79年盤はSumi-eという違いがある。内容もカルテットとビッグバンドで全く異なる。3曲中①②はフルート、③がテナーで、タバキンのフルートは和風になり過ぎずちょうどいい感じで、テナーもロリンズ、コルトレーン、ジョーヘンあたりに近い感じで好ましい。秋吉のピアノもいつもと違いモーダルであったりアブストラクトであったりで、全体にグルーヴもあり、よくまとまった盤になっていると思う。ペースとドラムもいい。クラブ系にも人気があるようで、CD化が切望される盤だ。(hand)
抽象的で難解な音楽のような先入観があった。特にフルートのA面への毛嫌いをイメージしていたが、意外とメロディアスで美しい旋律は受け入れやすかった。B面のほうがややフリーキーで、私のような保守的なジャズファンには、A面のフルートのほうが聴きやすい。(しげどん)
邦楽!?尺八!?を思わせるルータパキンのフルートからのスタートに戸惑うが、ユニークで日本らしさを表現した秋吉のアイデアに溢れる有名盤。少し奇を衒い過ぎて、聴きどころに悩む部分があるが、JAZZ界にJapanの風を吹き込んだ功績は大きい。(ショーン)
SOLO PIANO / 秋吉敏子
秋吉敏子(p)
聴きごたえ十分の初のソロピアノ盤
圧倒的なピアノ圧のようなものを感じるソロピアノ盤。これまで、曲単位でのソロ演奏はあったが、盤としては初。強烈に印象が残る ①ザ・ヴィレッジを始め、素晴らしい演奏が続々と聞かれる。秋吉のバドを知る前のアイドルであったテディ・ウィルソン的なスタイルから得意のビバップ、そして多少クラシカルな演奏も聞くことができる。今回、初めて聞いて、もっと早く聞けばよかったと後悔し、今後の愛聴盤になる予感がした。名盤だと思う。(hand)
オリジナルからスタンダードと、様々な曲で秋吉敏子の技巧が聴けるピアノソロ。スコット・ジョプリンのラグタイムなどもあり意外な感じがしたが、様々なスタイルを吸収して成り立っているトシコさんのスタイルの源泉を垣間見る気がした。(しげどん)
力強いタッチで、叙情的なストーリーや弾むような喜びが表現され、クラシカルな雰囲気があり、聴きごたえは十分。特にバラードでの、美しくこぼれ落ちるようなメロディは、冒険的なドキドキ感とメインに帰巣する安心感が同居しており、秋吉敏子らしさに溢れていて、価値ある素晴らしいアルバムだ。(ショーン)
KOGUN 孤軍 / TOSHIKO=TABACKIN BIG BAND
秋吉敏子(p,ldr), Lew Tabackin(ts),
Tom Peterson(ts), Dick Spencer, Gary Foster(as), Bill Perkins(bs),
Bobby Shew, John Madrid, Don Rader, Mike Price(tp),
Charles Loper, Jim Sawyer, Britt Woodman(tb), Phil Teele(b-tb),
Gene Cherico(b), Peter Donald(ds)
Scott Ellsworth(voice:2)
和のテイストが強烈なトシコ=タバキン・ビッグバンドの初盤
トシコ=タバキン・ビッグバンドの初盤で、秋吉としてのビッグバンドも正式には初。「ジャズ・イン・ジャパン」のような臨時編成盤はあったが、恒常メンバーによるリハーサルバンドは初。これまで何度も演奏された①エレジー、が大編成で生まれ変わっている。②メモリー、はアランフェスに似た名曲の名演だが、ボイスは苦手だ。ルバング島の小野田さんにちなんだタイトル曲③は鼓のヨーポンで和のテイストを出している(ヨーポンの初登場。1回目)。私は、正直あまり得意でないが、邦楽的要素の初採用だ。秋吉ビッグバンドはソロとアンサンブルのバランスがとてもいい。(hand)
トシコ・ビッグバンドはトシコさんの曲を演じるためのビッグバンドなので、作品重視。なので、特にメッセージ性が強い楽曲が注目を集めるのだと思う。でも単純なジャズファンの私は、エレジーのようなオリジナルに魅力は感じるが、ボーカルを加えたメモリーや、和楽器入りの孤軍などは、高い音楽性が評価されているのだろうが、愛聴するのは難しいというのが正直な感想だ。(しげどん)
LONG YELLOW ROAD / TOSHIKO = TABACKIN BIG BAND
秋吉敏子(p,ldr), Lew Tabackin(ts,fl,piccolo),
Stu Blumberg, Lynn Nicholson, Bobby Shew, John Madrid, Don Rader, Mike Price(tp),
Bruce Paulson, Charles Loper, Jim Sawyer, Britt Woodman(tb), Phil Teele(b-tb),
Dick Spencer(as,fl,cl), Gary Foster(as,ss,fl,cl), Joe Roccisano(as), Tom Peterson(ts,a-fl,cl), Bill Perkins(bs,a-fl,cl),
Gene Cherico(b), Peter Donald, Chuck Flores(ds)
Tokuko Kaga(vo:5)
トシコ=タバキン・ビッグバンドの第2作
トシコ=タバキン・ビッグバンドの第2作。前作「孤軍」と同じく、オリジナルのタイトル曲①の生まれ変わり演奏からスタートする。いい感じのビッグバンド盤と思い聞いていると、⑤カンチョリン?で足元を掬われた感じになる。私の苦手な強烈な和のテイストの登場だ。この民謡のような歌さえなければ、5★ランクに位置付けたい盤だ。(hand)
TALES OF A COURTESAN(Oirantan) 花魁譚 / TOSHIKO = TABACKIN BIG BAND
秋吉敏子(p,ldr), Lew Tabackin(ts,fl,piccolo),
Bobby Shew, Steven Huffsteter, Mike Price, Richard Cooper(tp),
Jim Sawyer, Bill Reichenbach Jr., Britt Woodman(tb), Phil Teele(b-tb),
Dick Spencer(as,fl,cl), Gary Foster(as,ss,fl,cl,a-cl), Joe Roccisano(as), Tom Peterson(ts,a-fl,cl), Bill Perkins(bs,a-fl,cl),
Don Baldwin(b), Peter Donald(ds)
和のテイストがやわらぎ聞きやすくなったトシコ=タバキン・ビッグバンドの第3作
トシコ=タバキン・ビッグバンドの第3作。まずはバリやバストロなどの低音が強化された印象だ。そして、和のテイストや難解さが柔らぎ普通のビッグバンド化したと思う。ただ、一般のビッグバンドも演奏できそうなビッグバンド曲が増えたと思う。「花魁譚」のタイトルから強烈な和のテイストを想像していたので、ある意味、ほっとした。秋吉の著書を読むと、日本人がアメリカ人と同じジャズをやってもしょうがない。日本人のルーツに根ざしたジャズをやるべきと考えたとのこと。この考え方には賛成する。ただ、孤軍のように「ヨー、ポン」までやるとなると、私自身は正直なところなかなか馴染めない。秋吉のそんな作品が日本で評価が高い割にあまり売れていないのは、日本のジャズファンの私と同じような心理も、働いているのではと思う。私もこれまではトリオやコンボを中心に秋吉ジャズを聞いてきた、というのも若い時に多分FMだと思うが、孤軍と思われる演奏を聞いてから、強烈な和のテイストの秋吉ビッグバンドと思い込み、遠ざけてきた事実がある。今回の全部聞きで、孤軍の強烈な和のテイストが当該曲など数曲だけと知り、少し後悔し、損をした気持ちになった。FM等の選曲は大事だと思う。木更津甚句だった⑥ヴィレッジ、は直前の「ソロ・ピアノ」までは、ザ、が付いていたが、今回はただのヴィレッジとなりビッグバンド化された。勢いもスピード感もある演奏だ。(hand)
テーマ曲はストーリー性を感じる作品だが、私には難解だった。でも冒頭のRoad Time Shuffleをはじめ、その他のスタンダードはまるでベイシー楽団のような活気あるスイング感があり、すんなり受け入れられた。(しげどん)
楽しく勢いのある演奏で、身体がウキウキするリズムだ。ホーンたちの合唱が、素晴らしい。メリハリのある展開で、フルートやバリトンサックスのアクセントが効いている。秋吉の出番が少ないように思う。(ショーン)
ROAD TIME / TOSHIKO = TABACKIN BIG BAND
秋吉敏子(p,ldr), Lew Tabackin(ts,fl),
Bobby Shew, Steven Huffsteter, Mike Price, Richard Cooper(tp),
Jim Sawyer, Bill Reichenbach Jr., Jimmy Knepper(tb), Phil Teele(b-tb),
Dick Spencer, Gary Foster(as), Tom Peterson(ts), Bill Byrne(bs),
Don Baldwin(b), Peter Donald(ds)
Guests:堅田喜三久(kotsuzumi:Disc2②), 矢崎豊(ōtsuzumi :Disc2②)
トシコ=タバキン・ビッグバンドの第4作は、日本公演の2枚組
トシコ=タバキン・ビッグバンドの第4作。日本公演のライブ2枚組。Disc 1①チューニング・アップ、はメンバー紹介に続き秋吉が、今からチューニングをします、と言い実際にチューニングが始まり驚いているとそのまま曲になるという驚きの展開。スイングビッグバンドではなく、モダンビッグバンドなので、1人ずつが長いソロがある。実力者揃いで、それも楽しみの1つだと思う。Disc 2②孤軍、はこの曲だけのために、その手の教養がないのでどちらかわからないが能か狂言の2人をわざわざ呼んだ豪華版(申し訳ないが、私はあまり歓迎できなかった。ヨーポン2回目)秋吉自身のピアノのソロは少ないが、ビッグバンドリーダーとしての秋吉の実力がハイレベルであることが実感できた。ライブなのにとても音がいい。CDはかなりの入手困難盤だ。(hand)
INSIGHTS / TOSHIKO = TABACKIN BIG BAND
秋吉敏子(p,ldr), Lew Tabackin(ts,fl),
Bobby Shew, Steven Huffsteter, Mike Price, Richard Cooper, Jerry Hey(tp),
Bill Reichenbach Jr., Charlie Loper, Britt Woodman(tb), Phil Teele(b-tb),
Dick Spencer, Gary Foster(as), Tom Peterson(ts), Bill Perkins(bs),
Don Baldwin(b), Peter Donald(ds)
Guests:堅田啓輝(羯鼓:3), 観世寿夫(謡:4), 亀井忠雄(大鼓:4), 鵜澤速雄(小鼓:4), ミチル・マリアーノ(歌:4)
トシコ=タバキン・ビッグバンドの第5作は、再び強烈な和のテイストを導入
トシコ=タバキン・ビッグバンドの第5作。名盤とされ所有はしていたが今回初めて聞いた盤。④ミナマタが有名だが、この曲が和のテイストだけでなく、重い公害問題を扱っている社会性の高い曲なので、これまで気楽に向き合うことができなかった。ミュージシャンがどんな意識で曲を作るかは自由だが、リスナーとしては軽い気持ちでターンテーブルに載せられた方がありがたい、という実態はあると思う。前半①②が普通のモダンビッグバンド演奏で、しかもバンドリーダー秋吉のピアニストとしての側面が珍しく前面に出ているので好ましく聞いた。後半③④のアナログでいうB面が和のテイストを感じる面となっている。 ①スタジオJ、はトリオ盤「メニー・サイズ」の再演でビッグバンド化。②トランジエンス、はエリントンを感じるバラードで素晴らしい。③すみ絵、はこれまで聞いていた曲なので、秋吉名曲のビッグバンド化でスーッと耳に入ってきた。終わり近くに和楽器が多少聞こえるが気になるほどではなかった。問題の④ミナマタ、は組曲の長い演奏で、最初、少女の歌声は入るが、その後は普通のビッグバンド演奏となりほっとして楽しんでいたところ、やはり終わり近くに、今度は強烈に和のテイストが入ってきて驚いた。というのも、孤軍(Kogun)、と同じヨーポンが使われただけでなく(ヨーポン3回目)、お経のような咏いまであるのはつらいとしか言いようがない。能や狂言だけでなく、歌舞伎でさえも見たことのない、また見ようという気になったことのない私にはやはり違和感のある活用に聞こえてしまう。尊敬する秋吉さんには申し訳ないが正直な気持ちだ。(hand)
発表当時スイングジャーナルの年間最優秀賞になったと記憶している名盤。大作ミナマタが高い評価を受けているが、この受け止め方は個人差があると思う。私にはシンプルにビッグバンドジャズとして前半の3曲の方が楽しめる。(しげどん)
・新宿ジャズ談義の会 :穐吉敏子 CDレビュー 目次
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作①1953-1958
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作②1960-1968
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作③1970-1976・・・このページ
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作④1976-1979
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作⑤1980-1987
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作⑥1990-1996
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作⑦1997-2005
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作⑥2006-2018