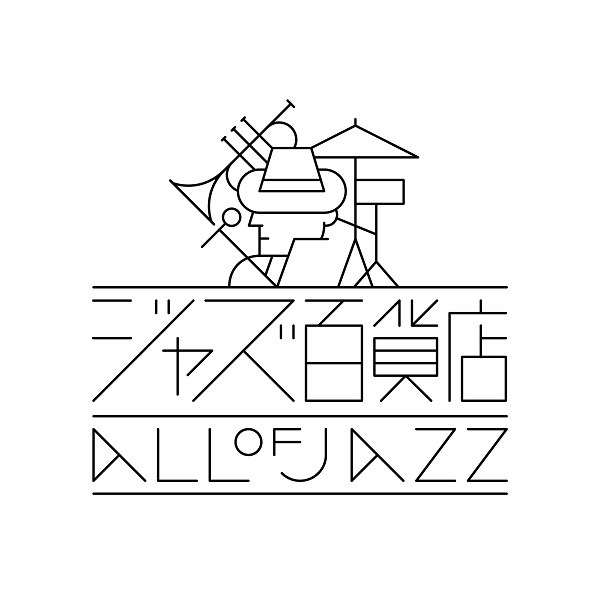Toshiko Akiyoshi 穐吉敏子 おすすめCD名盤&全リーダー・サイド作レビュー
秋吉(龝吉)敏子は、1929年、満洲(現、中国東北部)に生まれ、戦後に大分県に引き揚げジャズピアニストとして活動をスタートしました。48年に上京後、53年にオスカー・ピーターソンに見い出され、ノーマン・グランツのプロデュースでデビュー録音。56年渡米しボストン、バークリー音楽院に入学。59年ニューヨークに移り、チャーリー・マリアーノとトシコ=マリアーノ・カルテットを結成、結婚。62年ミンガス・バンドに参加。69年にルー・タバキンと再婚。73年にロスでトシコ=タバキン・ビッグバンドを結成。82年にはニューヨークへ戻り、83年に秋吉敏子・ジャズ・オーケストラを結成。2003年オーケストラを解散し、現在までピアニストとして活動しています。大リーグの大谷選手よりも50年前に、ピアニストとビッグバンドリーダーの二刀流でアメリカで勝負してきた秋吉さん。日本発(初)のジャズ・レジェンドとして、並び立つ人がいません。今回は、初めて日本人アーチストに焦点を当てて談義してみました。(しげどん)
ピアニストとしての秋吉敏子は昔から好きで聞いてきたが、和のテイストの強い(強過ぎる)と思っていたビッグバンドは敬遠してきた私handは、この新ジ談プロジェクトのために、秋吉のほぼ全ての録音の経年順に聞いていった。ピアニストとしては、バド系のバッパーから始まり好みの作品が数多く、オススメ盤の選考に困るほどであった。ビッグバンドについては、やはり和のテイストの強い盤というよりもいくつかの曲については、やはり苦手であった(秋吉さん、ごめんなさい)。ただし、ビッグバンドジャズとしてはかなり素晴らしいものが多く、食わず嫌いを反省した。
今回の談義結果は、多くの過去からの秋吉ファンには、いわゆる秋吉銘柄の名盤が選ばれず想定外ともいえる結果だと思うが、私たち(素人)の耳が選んだ、愛聴盤にしていきたいオススメ盤と言うことで理解いただけると思う。1位は非正規録音ながら演奏の持つ熱量が圧倒的なトリオ盤「陸前高田」となった。2位はジャズ・オーケストラの最終盤で日野皓正をゲストに迎えた「ラスト・ライブ・ブルーノート東京」。3位はピアニストとしての秋吉を堪能できる「ソロ・ピアノ」。4位はソノシートが原盤のトリオ盤「黄色い長い道」。5位は素晴らしい内容でCD化が切望されるカルテット盤「すみ絵」となった。
以下は、ソロ盤では「ソロ・ライブ・アット・ケネディ・センター」、「マイ・ロング・イエロー・ロード」、トリオ等盤では「メニー・サイズ」、「シック・レディ」、「ライブ・アット・ブルーノート東京’97」、ビッグバンド盤では「花魁譚」、「マーチ・オブ・タッドポ-ルズ」、「ニューポート’77」、「塩銀杏」、「テン・ガロン・シャッフル」等の多くの盤が最後まで選考に残り、本当に選考に苦心した。モダンジャズの夜明け盤「モカンボ」も健闘した。(hand)
・新宿ジャズ談義の会 :穐吉敏子 CDレビュー 目次
・Toshiko Akiyoshi おすすめBest5・・・このページ
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作①1953-1958
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作②1960-1968
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作③1970-1976
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作④1976-1979
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作⑤1980-1987
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作⑥1990-1996
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作⑦1997-2005
・Toshiko Akiyoshi CDリーダー作⑥2006-2018
おすすめ盤1位:1980 IN RIKUZENTAKADA 1980 イン・陸前高田 / 秋吉敏子トリオ
秋吉敏子(p), Bob Bowman(b), Joey Baron(ds)
秋吉の凄さが伝わる迫力あるピアノトリオ・ライブ
ピアノトリオのライブで、とても力強い。ライブ作品として素晴らしい構成になっていて、名曲Long Yellow Roadからはじまり、歌物スタンダードのOld Devil Moonからミルドレッド・ベイリーの名唱が印象深いI Let A Song...それから再びオリジナル曲。いいです。ビッグバンドでは作り込まれたオリジナル作品主体だが、このようなオーソドックスなピアノトリオの秋吉さんの凄さがわかるライブだ。 (しげどん)
ライブを主催した陸前高田ジョニー(現、開運橋のジョニー)の照井さんが秋吉の許可なく録音した音源を、後に許可を得て正式発売した盤。海賊録音なので、多少の難がある部分はあるが、とにかく内容が素晴らしい。会場の熱気に応えて、秋吉をはじめとするメンバーが熱演を繰り広げる。秋吉のMCが素晴らしいので長く収録されているが、別トラックになっているのでそれはいい。ただ、曲のクレジットミスがここまで多い盤は日本では珍しい。(hand)
迫力のライブ。秋吉敏子のパワフルなノリと踊り狂うリズムが、キレの良いJAZZを聴かせてくれる。秋吉の自由なアドリブにJoey BaronのベースとBob Bowmanのドラムスの息はバッチリで、それぞれのきめ細かい技が冴え渡る極めて爽快で心地良い演奏ばかりの名盤だ。また秋吉敏子の生のMC、当時の彼女の気持ちも残されていて、とても貴重な音源といえる。(ショーン)
おすすめ盤 2 位: LAST LIVE IN BLUE NOTE TOKYO ラスト・ライブ・イン・ブルーノート東京 / TOSHIKO AKIYOSHI JAZZ ORCHESTRA 秋吉敏子ジャズ・オーケストラ
秋吉敏子(p,ldr), Lew Tabackin(ts,fl),
Mike Ponella, John Eckert, Jim O'Conner, Jim Rotondi(tp),
Dan Levine, Steve Armour, Pat Hallaran(tb), Tim Newman(b-tb),
Dave Pietro, Jim Snidero(as,fl), Tom Christensen(ts,fl,ss), Scott Robinson(bs,ss), Paul Gill(b), Andy Watson(ds)
Guest:日野皓正(tp)
日野皓正をゲストに迎えたジャズ・オーケストラの第8作(ラスト盤)
ジャズ・オーケストラの第8作で一応のラスト盤(2010年に上海公演のために臨時で再結成される)。好ましいピアノトリオのビバップ演奏から始まる①レディ・リバティ、短いフルートに続きアルトソロ。遅れて出てくるタバキンのテナーがいつものワイルドではないのもいい。白人ながら黒人のテキサステナー的なソロが出てくると秋吉オーケストラの気品のようなものが薄まる気がする。タバキンは幽玄過ぎるフルートとブレンドして欲しいと失礼ながら常々思ってしまう。④⑤では日野皓正がゲスト出演して素晴らしいソロを聞かせてくれる。ゲストが入ることで選曲もアレンジも変わり統制が緩くなる。聞く方には、そのくらいが聞きやすいのだと思う。この盤は、私の苦手な部分がなく、素晴らしいモダン・ビッグバンド盤に思える。(hand)
ビッグバンドでありながら、少人数の編成バンドのようなきめ細やかな演奏で、独自の世界観のあるライブ演奏。秋吉らしい和の雰囲気とエスニカルな感覚が面白い。unrequited loveにおけるルー・タバキンのフルートと日野皓正のトランペットが素晴らしい。(ショーン)
ビッグバンドを辞めることにして、最後のツアーということなのでラスト・ライブ。でもメンバー全員リラックスというより吹っ切れたようにさわやかに元気なジャズを聴かせてくれる。(しげどん)
おすすめ盤 3 位:SOLO PIANO ソロ・ピアノ / 秋吉敏子
秋吉敏子(p)
聴きごたえ十分の初のソロピアノ盤
力強いタッチで、叙情的なストーリーや弾むような喜びが表現され、クラシカルな雰囲気があり、聴きごたえは十分。特にバラードでの、美しくこぼれ落ちるようなメロディは、冒険的なドキドキ感とメインに帰巣する安心感が同居しており、秋吉敏子らしさに溢れていて、価値ある素晴らしいアルバムだ。(ショーン)
圧倒的なピアノ圧のようなものを感じるソロピアノ盤。これまで、曲単位でのソロ演奏はあったが、盤としては初。強烈に印象が残る ①ザ・ヴィレッジを始め、素晴らしい演奏が続々と聞かれる。秋吉のバドを知る前のアイドルであったテディ・ウィルソン的なスタイルから得意のビバップ、そして多少クラシカルな演奏も聞くことができる。今回、初めて聞いて、もっと早く聞けばよかったと後悔し、今後の愛聴盤になる予感がした。名盤だと思う。(hand)
オリジナルからスタンダードと、様々な曲で秋吉敏子の技巧が聴けるピアノソロ。スコット・ジョプリンのラグタイムなどもあり意外な感じがしたが、様々なスタイルを吸収して成り立っているトシコさんのスタイルの源泉を垣間見る気がした。(しげどん)
おすすめ盤 4 位:RECITAL 黄色い長い道 / 秋吉敏子
秋吉敏子(p), Gene Cherico(b), Eddie Marshall(ds)
ロング・イエロー・ロードを含む5年ぶりの日本でのトリオ録音
オリジナルは朝日ソノラマのソノシート。前年のトシコ・マリアーノ・カルテットで演じた代表曲ロング・イエロー・ロードをピアノトリオで再演。Villageのタイトルでその後しばしば再演される木更津甚句など日本的な要素をジャズ的に表現しているが、純粋なピアノトリオ作品として楽しめる。(しげどん)
3人の息はよく合っており、ブレイクするところ等の技はなかなかだ。秋吉のピアノメロディは、時に軽やかでポップ。ジャズというより、イージーリスニング的な感覚もあり、自由な音楽を感じる。ドラミングも意識してしているのか、和心というか東洋的なエスニカルな感じが表現されていて面白い。(ショーン)
5年ぶりの帰国時の日本録音。黄色いLPジャケにはRecital 秋吉敏子リサイタルと書かれているが、帯には黄色い長い道、と書かれている。タイトルはリサイタルだがスタジオ録音。元はソノシート片面1曲の4枚組で朝日ソノラマの別冊として日本向けに発売されたもの。長らく「幻の録音」となっていたが、1977年にタムというレーベルから1988年にキングからLPとCD化され、2010年にスタジオ・ソングスからCDが再発された。秋吉得意の和のテイストとモーダルな雰囲気も取り入れられた素晴らしいトリオ盤だ。①黄色い長い道、はその後、ロング・イエロー・ロード、として秋吉のシンボルのような曲となっていく。「トシコ・マリアーノ・カルテット」で発表されたのが最初だ。②箱根のたそがれ、は秋吉のピアノだけでなく、ベースとドラムがとてもカッコいい。③木更津甚句、は後に左手のアレンジが強調されて、ザ・ヴィレッジ、となるが初演のこの盤は左手のベースフレーズは聞かれるが、木更津性がまだかなり残っている。①黄色い長い道②箱根のたそがれ③木更津甚句⑤ディープ・リヴァーが元の別冊ソノシート(260円)で、④ソルページ・ソング(ソルヴェーグの歌)は、朝日ソノラマの別冊ではなく、昭和36年4月号(360円)で発表されている。元盤が5枚のソノシートということでトータル時間が短いのが残念なところだが、音はいい。和のテイストが後年のビッグバンド期の強烈さがなく、程よく味わえるのがいい。(hand)
おすすめ盤 5 位:SUMIE すみ絵(LP) / 秋吉敏子カルテット ← The Personal Aspect In Jazz(4channel LP)
1971.3.4
日Victor


おすすめ度
hand ★★★★★
しげどん ★★★☆
ショーン ★★★★
秋吉敏子(p), Lew Tabackin(ts,fl), Lyn Christie(b), Albert Heath(ds)
CD化が切望される和のテイストが自然な盤
元盤は当時流行しそうであった4チャンネル用LPで、タイトルは「ザ・パーソナル・アスペクト・イン・ジャズ」(1971年)で、秋吉の演奏姿ジャケ。4チャンネル専用プレーヤーでしかかからないレコードであったため、4チャンネルの衰退とともに聞けない盤となっていた。これを通常のステレオ盤LPとして77年に再発売したのが「すみ絵」でジャケはローマ字でSumieの文字。8年後の79年に発売の「すみ絵」とは、日本文字は同じだがローマ字が異なり、こちらがSumieで79年盤はSumi-eという違いがある。内容もカルテットとビッグバンドで全く異なる。3曲中①②はフルート、③がテナーでタバキンのフルートは和風になり過ぎずちょうどいい感じで、テナーもロリンズ、コルトレーン、ジョーヘンあたりに近い感じで好ましい。秋吉のピアノもいつもと違いモーダルであったりアブストラクトであったりで、全体にグルーヴもあり、よくまとまった盤になっていると思う。ペースとドラムもいい。クラブ系にも人気があるようで、CD化が切望される盤だ。(hand)
邦楽!?尺八!?を思わせるルータパキンのフルートからのスタートに戸惑うが、ユニークで日本らしさを表現した秋吉のアイデアに溢れる有名盤。少し奇を衒い過ぎて、聴きどころに悩む部分があるが、JAZZ界にJapanの風を吹き込んだ功績は大きい。(ショーン)
抽象的で難解な音楽のような先入観があった。特にフルートのA面への毛嫌いをイメージしていたが、意外とメロディアスで美しい旋律は受け入れやすかった。B面のほうがややフリーキーで、私のような保守的なジャズファンには、A面のフルートのほうが聴きやすい。(しげどん)