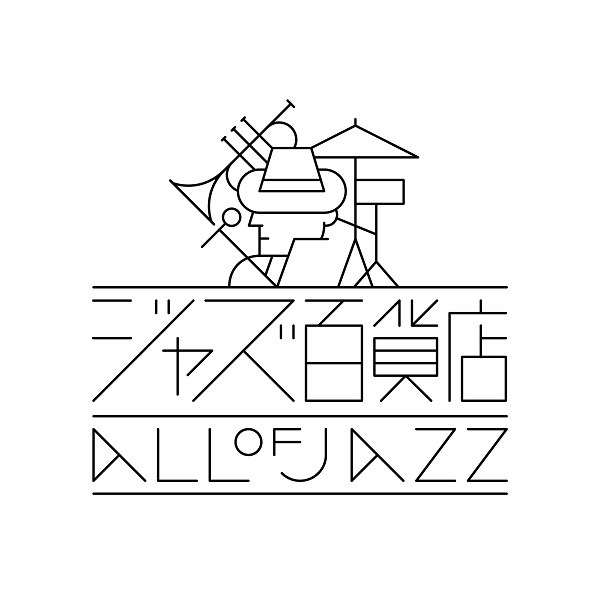Thelonious Monk セロニアス・モンク おすすめCDレビュー リーダー作 7
このページでは1967年から最終作品までを紹介しています。
この時期の特筆すべきは、67年秋の九重奏団(ノネット)での欧州ツアーです。正規録音はありませんが、海賊盤数枚がとてもいい出来です。いつものカルテットにフィル・ウッズ、ジョニー・グリフィンらの豪華メンバーが加わったもので、リバーサイド時代の「タウンホール」よりも内容は濃いと思います。
68年で売行きの問題か健康の問題か不明ですが、コロンビアとの契約が終わります。その後は、決まったレーベルではなく、その時にオファーのあったレーベルとフリーランスで録音したのだと思います。60年頃から約10年付き合ったチャーリー・ラウズも遂に脱退し、ポール・ジュフリーが加わったりしますが長続きしません。2020年発掘された68年録音の「パロ・アルト」が人気盤となっているのは喜ばしいことです。
セロニアス・モンク CDレビュー目次
①リーダー作 その1 初リーダー作からリバーサイド時代前半1957年まで
②リーダー作 その2 リバーサイ時代続き 1957年~1958年
④リーダー作 その4 後期 コロンビア移籍後 1962年~63年
Live in Rotterdam/Thelonious Monk
Thelonious Monk(p),Charlie Rouse(ts),Larry Gales(b),Ben Riley(ds),
Clark Terry, Ray Copeland(tp),Jimmy Cleveland(tb),Phil Woods(as),Johnny Griffin(ts)
この後の「イン・ヨーロッパ」や「ノネット」と同時期のオランダでの九重奏団ライブ。快演だ!
2017発掘の放送用音源と思われる音のよいCD2枚組。カルテットにジョニー・グリフィン、フィル・ウッズ、クラーク・テリーらがホーンズとして加わり、ソロもとる。長尺演奏が多く、各メンバーのソロが十分に楽しめる。モンクも楽しそうで、張り切ったソロが聞かれる。このメンバーでの公式録音がないので、この音源は貴重だと思う。(hand)
In Europe(LP)/Thelonious Monk
1967年10月28日他
Unique Jazz

未CD化 リンクはありません。
hand ★★★☆
Thelonious Monk(p),Charlie Rouse(ts),Larry Gales(b),Ben Riley(ds),
Clark Terry, Ray Copeland(tp),Jimmy Cleveland(tb),Phil Woods(as),Johnny Griffin(ts)
67年のノネットでのヨーロッパ海賊ライブ
未CD化。海賊レーベルのユニーク・ジャズ。内容はいいが音は悪い。4曲中3曲は前出の「ロッテルダム」と同じものかもしれない。B2は、ハッケンサックと表示されているが、ウィーシーの誤り。(hand)
Nonet Live in Paris 1967/Thelonious Monk
Thelonious Monk(p),Charlie Rouse(ts),Larry Gales(b),Ben Riley(ds),
Clark Terry, Ray Copeland(tp),Jimmy Cleveland(tb),Phil Woods(as),Johnny Griffin(ts)
ノネット(九重奏団)による67年11月3日のパリの海賊ライブ
ノネット(9重奏団)による67年11月3日のパリの海賊ライブ。モンクは正式なビッグバンド(17人編成)よりも、スモール・ビッグバンドというか、ビッグ・コンボが好みだったようで、時々編成している。大編成のモンクの演奏はまさに錚々たる面々のビッグ・コンボという感じで、いつものカルテットを拡大してソロイストを増やして曲の色合いを濃くしている。モンクの尊敬するエリントンのような重厚なアンサンブルを求めてはいないと思う。事実、①ルビーマイディアはいつものカルテット、②ウィシーでトランペットのコープランドのみ加わる。この2曲がCD化で追加された曲だ。③エピストロフィでグリフィン、コープランドが加わりソロがある。エンディングはもう少し大人数のようだ。④オスカTではテーマが多少重厚なので全員と思われる。コープランド、グリフィン、クリーブランドのソロがある。⑤エビデンスは、ラウズ、テリー、ウッズのソロがある。ラウズのソロがグリフィンの影響かいつもより饒舌に感じる。⑥ブルーモンクはテリーのフリューゲルのミュート演奏。以上、全てに当然モンクのソロもあり、ベース、ドラムのソロのある曲もある。ライリーもビッグバンドらしいドラムを叩く。放送用録音なので音はまずまず。現在は、セロニアス・レーベルから「ライブ・イン・パリ Vol.3」となって出ているが既に入手困難のようだ。(hand)
Underground/Thelonious Monk アンダーグラウンド/セロニアス・モンク
Charlie Rouse(ts),Thelonious Monk(p),Larry Gales(b),Ben Riley(ds)
コロンビアのスタジオ録音7作目。久々に新曲3曲が入る。
コロンビアのスタジオ録音7作目。68年に終わるコロンビア時代の最後3年間は毎年スタジオ録音している。ポップカルチャーなのかもしれないが趣味の悪いジャケだと思う。普通のアーチストの場合、スタジオ新譜では旧曲をそのまま演奏することは稀だが、モンクの場合、旧曲の間にたまに新曲(この盤では、ブー・ブーズ・ダイアリーという娘のための曲と、ライズ・フォー・サンセット、アグリー・ビューティ)が混じる程度のものが多く、この辺はどう理解すればいいか悩ましいが、ソロが違えばいいということなのかもしれない。ラスト⑦イン・ウォークド・バドは私のお気に入り曲なのだが、男性バップボーカルが入り、馴染みにくい。(hand)
タイトルとかジャケデザインとかはモンクの反骨精神の表現!でもこの手の込んだジャケット画は大手コロンビアだからできた。本当はプレスティジ盤の手抜きジャケットのほうがリアルにアングラなのだが・・・ そして、内容はやはりリバーサイド時代のような凄みはすでになく、音楽的には角が取れたリラックスして聴けるモンク。ラウズもリズムセクションもモンクを良く理解しているので、まとまりがあり洗練された感じで、それはコロンビア時代のスタジオ盤の共通した印象だ。それでもモンクらしくはあるのだけれど・・・ このジャケデザイン画中で得意げにピアノを弾くモンクの姿は好きなので、ジャケ買いする値打ちはあるかもしれない。(しげどん)
PALO ALTO/Thelonious Monk
Thelonious Monk(p),Charlie Rouse(ts),Larry Gales(b),Ben Riley(ds)
2020年インパルスからの発掘盤。熱い演奏で、新たな名盤の誕生ともいえる。
パロアルトという名は、以前リッチー・コールらの盤を出していたレーベルとして知られるが、この盤はレーベルはインパルスで、モンクの最新2020年の発掘盤だ。サンフランシスコ近郊の町パロアルトの高校生が人種差別撤廃運動のコンサートをしたいとモンクに電話したことから実現したライブだ。1968年10月27日、モンク・カルテットの好調の時期を捉えた録音で、特に②ウェルユーニードントは、13分超の長尺でベース、ドラムのソロ熱演も聞かれて圧巻だ。素人録音ながら音もよく、後処理なのかもしれないが、リアルな音像を感じることができる。(hand)
Monk’s Blues/Thelonious Monk モンクス・ブルース/セロニアス・モンク
Charlie Rouse(ts),Thelonious Monk(p),Larry Gales(b),Ben Riley(ds),
Robert Brookmeyer,Robert Bryant,Conte Candoli,Frederick Hill(tp),William Byers,Mike Wimberly(tb),Ernie Small,Ernest Watts,Gene Cipriano,Thomas Scott(sax),Howard Roberts(gr),John Guerin(perc),Oliver Nelson(arr,conductor)
コロンビアのスタジオ録音8作目でラスト録音は、オリバー・ネルソン指揮のストリングス入りジャズオーケストラ作品
コロンビアのスタジオ録音8作目でラスト録音。タイトルからブルース特集で黒っぽい作品かと思うと、そうではない。カルテットにオリバー・ネルソン指揮のストリングス入りジャズオーケストラをつけた作品で、どちらかというと明るい印象の盤。③リトル・ルーティ・トゥーティではトランペットソロやサックスソリもある。テオ・マセロなのでクリード・テイラーのようなイージーリスニングにはなっていない。これまであまり評価されていない盤だと思うが、私の印象は悪くない。ピアノは、明るめに録音されている。(hand)
コロンビア時代のモンクは親しみやすくなった反面、毒気を抜かれた感があるのは、多くのファンの認識だ。それはやはり大手コロンビアの意図=大衆受けを狙った企画のためだと思うが、この最終作はその集大成とも言えるオーケストラとの共演である。あの難解な「ブリリアント・コーナーズ」などは曲は同じでも別物に聴こえる。でもオリバー・ネルソンのアレンジはさすがで、これはこれできちんとしたジャズになっている。しかしすべてを支配していた今までのモンクのイメージはなく、逆にオーケストラに支配された形で一生懸命ピアニストをしている。このような形でモンクの曲がポピュラリティを得れるとは到底思えないが、モンクファンにとっては逆に特異な作品ではあると思う。(しげどん)
PARIS 1969/Thelonious Monk パリ 1969/セロニアス・モンク
Thelonious Monk(p),Charlie Rouse(ts),Nate Hygelund(b),Paris Wright(ds),"Philly" Joe Jones(ds:⑪⑫)
録音が少ない69年の貴重なパリ公演の海賊発掘盤。後半2曲がフィリーとの珍しい共演
1969年は録音が少ない年。これはパリ公演の海賊発掘盤で、動画入りの2枚組もある(私のはCDのみ。)。69年はラリー・ゲイルズとベン・ライリーが去り、ラウズのみがしばらく残っていた時期。このため、パリの現地の元気のいいベース&ドラムとの共演となっている。画像を見ていないが、若手と思われる2人の張り切りでモンクもラウズも刺激を受けている。中半にピアノソロをはさみ、後半2曲がフィリーとの珍しい共演。フィリーとの共演は、ありそうだが、意外と少なく、クラーク・テリーの「イン・オービット」のみかもしれない。フィリーは、私好みの暴れドラムで、モンクをうまい具合に煽っていて、⑪ナッティはなかなか楽しい。⑫はエンディングで短い。(hand)
IN TOKYO(LP)/Thelonious Monk セロニアス・モンク・イン・トーキョー
70.10.24
Toshiba/Express

リンクはありません。
hand ★★★
Thelonious Monk(p),Paul Geffreys(ts),Larry Redley(b),Lenny McBrowne(ds)
ラウズが脱退し、ポール・ジュフリー加入後の70年来日公演の記録
ラウズが脱退し、ポール・ジュフリー加入後のライブ。ジュフリーは可もなく不可もなくという感じ。ラウズの音に慣れた耳に新鮮に響くかと思ったが、残念ながら新鮮さよりも違和感を感じてしまった。ベースがラリー・ゲイルズから同じラリーだがラリー・リドレーに変わり、ドラムもベン・ライリーからレニー・マクブラウンに変わっているのも一体感が減った原因だと思う。モンク自身のプレイはあまり変わっていない。(hand)
London Collection/Thelonious Monk コンプリート・ラスト・レコーディングス/セロニアス・モンク
Thelonious Monk(p),Al McKibbon(b:Disc 2:1-13),Art Blakey(ds:Disc 2:1-13)
公式録音としては最後の録音。ジャイアンツ・オブ・ジャズの一員として世界ツアー中のモンクを、ブラックライオンレーベルがロンドンでソロとトリオで録音
近年までラストレコーディングとされていた作品。これ以降の録音は非公式のものなので、公式録音としては最後の録音であることに変わりはない。ジャイアンツ・オブ・ジャズの一員として世界ツアー中のモンクを、ブラックライオンレーベルがロンドンでソロとトリオで録音した作品。トリオはジャイアンツからアル・マッキボンとブレイキーが参加している。20年前のモンクの最初期のブルーノート盤「ジニアス オブ モダン ミュージック Vol.2」のリズム隊と同じ組合せだ。当初は、「サムシング・イン・ブルー」、「ザ・マン・アイ・ラブ」、「ナイス・ワーク・イン・ロンドン」のアナログ3枚で発売されたが、CD化で2枚組になり、1枚目がソロ、2枚目がトリオ(最新盤にはソロ別テイク1曲追加)という形でコンプリート化された。1 ⑨ラバーマンは、選曲として珍しいが、ジャイアンツ・オブ・ジャズでカイ・ウィンディングが吹いていたので、それで気に入った可能性が高い。いつもはバラードをカラッと弾くモンクが、しっとりと弾いていると思う。トリオ編は、想像以上に元気な3人の演奏が聞かれる。ジャイアンツのリズム隊として、ディジーらのバッキング時間が長いので、鬱憤が溜まっていたのだろう。 モンク53歳、マッキボンとブレイキーが51歳で、皆元気なのはうれしいが、モンクはこれが最後の元気だったのかもしれない。また、この盤では、モンクの新曲が3曲も入っていることが貴重だ(ブルー・スフィア、サムシング・イン・ブルー、コーディアリー)。(hand)
とても感動的な2枚組だ。1枚目はソロ、2枚目はトリオでの録音で、かなりのボリュームがあるので、もともとのアナログ盤のように、ソロとトリオの曲がバランス良く配置されていた形のほうが、鑑賞的にはそちらのほうが聴きやすいかもしれない。でも、モンク最後の姿をとらえた貴重な音源なので、今日のようなコンプリート化は望ましいことだ。なぜならこのような形で聴くと、モンクのむき出しの原点をとらえた迫力ある記録であることがより意識され、つくづくコロンビアの諸作がイマイチだったのは企画的な意図が前に出過ぎていたためだったような気がするのだ。ジャイアンツ・オブ・ジャズのツアーは、最初はマックス・ローチを招聘する予定だったらしいので、この録音のためにはベスト・パートナーであるブレイキーが来てもらった事はよかった。残念ながら正式なスタジオ録音としては最後の作品になってしまったが、自由にのびのびと自曲を演ずるモンクは、単なる記録ではなく、なんども聞き返したくなる演奏の魅力に溢れている作品だ。(しげどん)
THE LAST CONCERTS/Thelonious Monk ラスト コンサート/セロニアス・モンク
1①〜⑥:Thelonious Monk(p),Paul Geffreys(ts),Larry Redley(b),T.S. Monk(ds)
1⑦〜⑨,2①〜⑦:Thelonious Monk(p),Paul Geffreys(ts),Dave Holland(b),T.S. Monk(ds)
2⑧〜⑩:Thelonious Monk(p),Charlie Rouse(ts),Larry Gales(b),Ben Riley(ds)
75年のリンカーンセンターでの録音と72年の珍しいデイブ・ホランド入りのバンガードでの録音からなる2枚組。現時点でのラスト録音
ジャイアンツ・オブ・ジャズのツアー中の1971年ロンドン録音がラスト・リーダー録音とされていたモンクだが、さらにその4年後の録音が2009年に発売された。1①〜⑥の75年のリンカーンセンターでのニューポートフェスのカルテット録音と1⑦〜⑨、2①〜⑦の72年の珍しいデイブ・ホランド入りのバンガードでのカルテット録音からなる2枚組。ラウズ退団後の東京録音に入っていたポール・ジュフリーがこの盤でもテナーを吹いている。ベースはラリー・リドレーで、ドラムは息子のT.S.モンク。東京から時間が経ち、ジュフリーの違和感はなくなり、むしろいい感じになっている。ラウズ入りカルテットがあまりにまとまっていたので、多少のまとまりの悪さのようなものがいい結果につながっている。これが普通のジャズライブだと思う。多少、弾けているから楽しいのだ。ホランド音源は、やや音が悪いが、ホランドの存在感はさすがだ。モンクに遠慮してか、弾きまくることはないが、重い音色で、動きのあるラインを描いている。T.S.のドラムの暴れ具合も楽しい。2⑧〜⑩にラウズ時代の66年のフランス録音がおまけとして入っている。(hand)