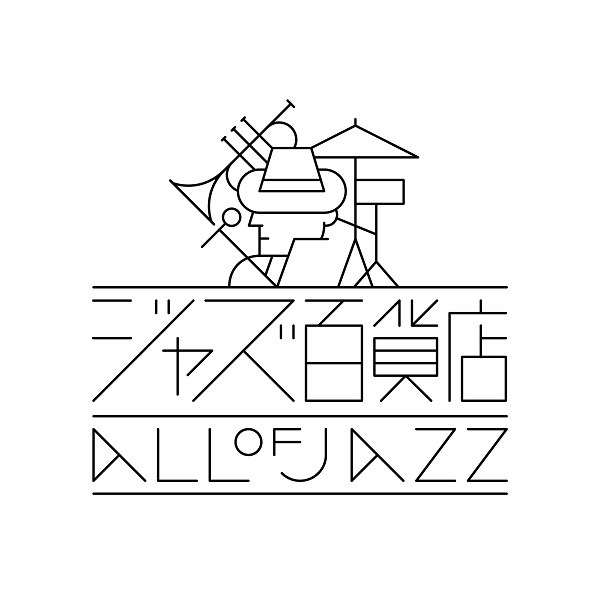Lou Donaldson リーダー作1 1952~1961年
クリフォード・ブラウンも入ったアート・ブレイキーの「バードランドの夜」はブレイキーの名盤というだけでなくモダンジャズの夜明けを象徴する歴史的な盤です。そのブレイキーのもとでバッパーとしてスタートしたルー・ドナルドソン(ルウドナ)。独立後、ワンホーンや2管、3管のハードバップを経て、オルガンやコンガ、ギターの入ったファンキージャズへと向かっていく初期10年についてコメントします。
・新宿ジャズ談義の会 :ルー・ドナルドソン CDレビュー 目次
・Lou Donaldson CDリーダー作 ①・・・このページ
QUARTET/QUINTET/SEXTET / Lou Donaldson
Lou Donaldson(as), Horace Silver(p:1-7), Elmo Hope(p:8,9), Blue Mitchell(tp:5-7), Kenny Dorham(tp:8,9), Matthew Gee(tb:8,9), Gene Ramey(b:1-3), Percy Heath(b:4-9), Art Taylor(ds:1-3), Art Blakey(ds:4-9)
初リーダーセッションを含む2枚の10インチ盤をまとめた盤
ブレイキーの「バードランドの夜」で、ハードボイルドなバッパーぶりを聞かせたルウドナが、初リーダー盤でバッパーとしての自らの音楽性を打ち出している。この盤は、3つのセッション(10インチ盤2枚)を1枚にまとめたので、盤としてのまとまりはあまりないのだが、印象は悪くない。特にアナログ時代と同じ10曲バージョンのCDは、別テイクも含めた15曲を録音順に収録したCDよりも数倍好印象だ。曲順がいかに大切かということだと思う。(hand)
初リーダーセッションを含む2枚の10インチ盤をまとめたもので、初期のルウドナ節が堪能できる好盤。A面にカルテット、クインテットの5021を、B面にセクステットの5055を収録しているが、時間の関係で一部B面にカルテットが入り、それぞれから一曲づつカットされている。A面は10インチ盤とほぼ同じ曲順だが、B面のセクステットは10インチ盤冒頭のAfter You've Goneがカットされていて、これが一枚を印象づける中々勢いのある演奏だったのでB面がやや印象薄な感じになった。メンバーのオリジナルを優先したためかも知れない。+5と表示されている現在のCDでは、別テイクも含めて、12インチ化の際にカットされた2曲も復活しているが、曲順が大きく変わってしまっている。A面カルテット、クインテットに於けるホレス・シルバーの硬派なサポートがなかなかはまっている。(しげどん)
ルードナルドソンの軽やかだけれども、決して薄っぺらくならないアルトは、マイナーキーを上手く使いこなしていて、 1950年代のパワーとお洒落な雰囲気が伝わってくる。貴重で大人を感じるいいアルバムだ。(ショーン)
Wailing With Lou/Lou Donaldson
Lou Donaldson(as), Donald Byrd(tp), Herman Foster(p), Peck Morrison(b), Art Taylor(ds)
デビュー盤から3年後のバランスの良いハードバップ盤
デビュー12インチ盤から3年後の1957年の第2作。この年からルウドナは急に多作家になる。74年で一旦途切れるが、毎年1~4枚を吹き込んでいる。57年は時代がハードバップ期に入り、前作よりもメロディやアレンジを重視した典型的なハードバップ盤になっている。特に①キャラバンは圧巻で、ルウドナとドナルド・バードの2管に加え、アート・テイラーがブレイキー的な熱いドラムを聞かせ、初期JM的な興奮が味わえる。この後、オルガンと組むことが多くなるルウドナだが、ピアノのときは基本的にハーマン・フォスターで、この盤がフォスターとの最初の盤となる。(hand)
ドナルド・バードとの2管で、バランスの良いハードバップ盤。冒頭の”キャラバン”は名曲すぎる上に個性が強い曲なので、その印象が強く残る一枚だが、私はThat Old Fellin’のようなウタモノでのルウドナが好きだ。(しげどん)
いきなり、荒々しいcaravanに乗せられてハードバップの小旅行に出たような疾走感と異国情緒を味わうことのできる素晴らしいアルバム。Lou DonaldsonのアルトにDonald Byrdのトランペットが熱く絡み、更にHerman Fosterの硬質のピアノが後方支援することで、ファンキー度バリバリのアルバムとなっている。(ショーン)
SWING & SOUL / Lou Donaldson
Lou Donaldson(as), Herman Foster(p), Peck Morrison(b), Dave Bailey(ds), Ray Barretto(conga)
3作目はワンホーンにコンガが加わる。
57年のリーダー盤は3枚で、この盤が2枚目。ワンホーンカルテットにコンガが加わってお気楽な感じのジャズだ。ルウドナの音色の明るさが際立つ。コンガも使いようによってはハードな雰囲気になるが、ルウドナの場合、終始くつろぎ系の使い方だ。ベースから始まるブルース⑦グリッツアンドグレイビーが冒頭にあれば、もっと印象が良かったのではないかと思う。ルウドナにバラード始まりは似合わない。(hand)
はじめて12インチLP一枚全部ワンホーンで通した作品だが、すでにコンガが入ってしまった。でもワンホーンのルウドナが味わえる好盤で、I Won’t Cry...のようなウタモノがなかなか聴かせると思う。スロー・テンポのバラードからはじまるが、それがこの一枚を地味な印象にしているのが残念だ。アルバムの一曲目は「つかみ」として重要なのだ。でもB面一曲目のThere Will Be・・・のように良く知られた曲をぐっとスローペースで演奏するのは悪くないし、最終曲のGrits...のようなスローなブルースは、逆にルウドナらしさが良く出ている。A面四曲目の Peck Time は 8年後にFRIED BUZZARDでも演奏していた。(しげどん)
LOU TAKES OFF / Lou Donaldson
Lou Donaldson(as), Donald Byrd(tp), Curtis Fuller(tb), Sonny Clark(p), Jamil Nasser(b), Art Taylor(ds)
ドナルド・バード、カーティス・フラーとの3管ハードバップ盤。ピアノはソニー・クラーク
57年の3枚目のリーダー盤は、ドナルド・バード、カーティス・フラーとの3管によるハードバップ盤。ピアノは、ソニー・クラーク。ルウドナ自身はややくつろぎを感じる演奏をしているが、他のメンバー、特にフラーは「ブルー・トレイン」的なハードボイルドなプレイで絶好調感がある。ジョージ・ジョイナー(ジャミール・ナッサー)のベースも私好みだ。唯一の難点は、選曲がビバップ過ぎるという点だと思う。ビバップは好みだが、57年にこのメンバーでここまでやる必然性はない。(hand)
カーティス・フラー、ソニー・クラークといったお気に入りの面々が参加しているジャム・セッションだが、冒頭の曲のソ連の人工衛星をテーマにしたSputnikの、なんだか煽り立てるような印象が好きではなかった。特にベースのジョージ・ジョイナーは私の好みではない性急な感じがする。むしろ二曲のビバップチューンは悪くはないし、B面冒頭のStrollin’のようなシンプルなブルースが一番好きな曲調だ。(しげどん)
BLUES WALK / Lou Donaldson
Lou Donaldson(as), Herman Foster(p), Peck Morrison(b), Dave Bailey(ds), Ray Barretto(conga)
初期ルウドナの最大ヒット盤
ルウドナの初期ヒット盤。タイトル曲①ブルース・ウォークのルウドナらしさ満載のルーズかつブルージーな感じが受けたのだと思う。コンガも効果的だ。時折、クリフォード・ブラウンの同名曲と誤解される場合があるが、ブラウニー曲は、"ザ・ブルース・ウォーク”。②ムーブはビバップだが、コンガが入り軽く明るい感じに仕上がり、パーカーの深刻さはない。全体にポップな雰囲気が漂っていて、アメリカでは受けても、暗いのが人気だった日本のジャズ喫茶全盛期にはあまり受け入れられなかったと思う。(hand)
前半のルウドナにとっては最大のヒット作だと言われている。しかしこの表題曲は哀愁が感じられず私好みではない。むしろミディアムテンポのスタンダード曲やMoveのようなバップスタンダードにジャズらしさを感じ、彼のアルトのストレートな魅力を感じる事ができる。(しげどん)
レイパレットのコンガが独特のアフリカンな雰囲気を醸しており、ルーのメロディアスなアルトとともに独自性の高い魅力的な曲が続く。autumn nocturneのようなしっとりと唄い上げる曲もあり、ルードナルドソンの渋いブルースを全編で楽しめるアルバムだ。(ショーン)
LIGHT-FOOT / Lou Donaldson
Lou Donaldson(as), Herman Foster(p), Jimmy Wormworth(b), Dave Bailey(ds), Ray Barretto(conga)
ヒット盤「ブルース・ウォーク」の陰に隠れた好盤
「ブルース・ウォーク」に続く1958年2枚目のリーダー盤。あまり聞いた記憶のない盤だが、聞いてみるとタイトル曲①のハードボイルドな感じが私には好感だ。中盤はナベサダの「カリフォルニア・シャワー」のような明るい感じにはなるが、許容範囲だ。(hand)
BluesWalkの続編のようなイメージで、引き続きコンガが入っているので軽いイメージではあるが、ジャズらしい粋を感じるワンホーンでの一枚。全体的には前作Blues Walkよりジャズらしさを感じる。(しげどん)
軽快な足取りそのままに、小気味よく響くリズム隊が主役のlight-footから始まり、しっかりアルトとピアノを聴かせるブルースhog man。多彩な表現が、雰囲気の良いメンバーで次々と演奏されてゆく。重たいjazzと異なり、フュージョン的な要素やブルース的な味わいが同居したこれも自然体で楽しいルーワールドなのだ。(ショーン)
LD + 3 / Lou Donaldson With The 3 Sounds
Lou Donaldson(as), Gene Harris(p), Andrew Simpkins(b), Bill Dowdy(ds)
ザ・スリー・サウンズとの共演盤はとてもジャジー
ジーン・ハリス率いる人気ピアノトリオ、ザ・スリー・サウンズとルウドナの共演盤。3サウンズの音楽性からファンキーな感じを想像するが、意外にも純ビバップなスタート。トリオで、コンガもいないので、ジャズ度も高い。ハリスも元はやはりバッパーだったと再確認した。同じビバップ的な「ルー・テイクス・オフ」と比べるとこちらが親しみやすい。ワンホーンで曲もアドリブもメロディアスなのではないかと思う。(hand)
スリーサウンズのサポートを得たオーソドックスなワンホーン作。コンガが入っていないオーソドックスなカルテット作はあまりないので貴重だ。選曲もスタンダード中心でルウドナさんのウタモノ解釈が楽しめる文句なしの好盤。(しげどん)
淀みなく流れるアルトの音色。安心して聴けるルードナルドソンの世界。アルバムの名の通り、プラスの3名は、ルーの演奏と世界観をしっかりサポート強化する役割に徹しており、アルバムのカラーは「地に足のついた軽快なハードバップ」として統一されている。(ショーン)
THE TIME IS RIGHT / Lou Donaldson
Lou Donaldson(as), Blue Mitchell(tp), Horace Parlan(p), Laymon Jackson(b), Sam Jones(b:3), Dave Bailey(ds), Al Harewood(ds:3), Ray Barretto(conga)
ブルー・ミッチェルとの二管ハードバップ盤。ピアノはホレス・パーラン
ブルー・ミッチェルのトランペットが入り、ピアノがハーマン・フォスターからホレス・パーランに変わる。ルウドナ盤常連のレイ・バレットのコンガが入っているが、合わない曲もあり、この盤にはコンガはいらなかったと思う。ただ、パーランが軽くなりがちな盤を重いピアノで引き締めている。(hand)
ブルー・ミッチェルとの二管で、全体的にいい感じだ。一曲目はデビュー作で演じていたオリジナルだが、全体ではスタンダードが多く採用されていて聴きやすいハードバップ作品。コンガを全否定するつもりはないが、でもスタンダード曲などにはつくづくコンガがなければなぁ、と思う瞬間が多々ある。ルウドナ、ミッチェル、パーランのソロのバランスが良いので、そこが残念だ。(しげどん)
SUNNY SIDE UP / Lou Donaldson
Lou Donaldson(as), Bill Hardman(tp), Horace Parlan(p), Laymon Jackson(b:1,2,4,5), Sam Jones(b:3,6-8), Al Harewood(ds)
ビル・ハードマンとの二管のハードバップ盤。コンガ抜きでジャズ度は高い。
60年代最初の盤。ピアノのホレス・パーランは引き続きで、トランペットがビル・ハードマンに変わる。この盤はコンガ不参加だが、コンガ入りでもいいと思える選曲もある。(hand)
前作と同様にトランペットとの二管だが、こちらのほうがずっと硬派のジャズらしい作品と感じていたのだ。ビル・ハードマンの好演もあるが、こちらはコンガが入っていないので、ぐっとジャズらしくなる。一曲目のオリジナルブルースがとてもかっこいい愛聴盤である。ルウドナのソロもファンキーな勢い満載のすばらしいものだ。(しげどん)
アルトサックスの音色の美しさを感じることのできるルードナルドソンのプレイが光る。アルバム名の通り、全体を通して明るく軽快だ。ポピュラリティのある耳に残るメロディは、重苦しさの微塵もなく、jazz初心者でも抵抗なく聴けるだろう。(ショーン)
MIDNIGHT SUN / Lou Donaldson
Lou Donaldson(as), Horace Parlan(p), George Tucker(b), Al Harewood(ds), Ray Barretto(conga)
ワンホーンの発掘盤。ピアノはとりあえずお別れに。
1980年の発掘盤。ワンホーンで、ピアノはパーラン、バレットのコンガも参加。パーラン参加は3作目でラストとなる。今後、オルガン時代に移り、時折のピアノ入り盤は、ハーマン・フォスターが戻る。この盤は、似たような盤が多い中で、オルガン時代となり未発となったと思われるが、割と出来はいいと思う。(hand)
LTシリーズで発売された発掘盤だが、中々の好演奏だ。ホレス・パーランとの顔合わせでは、これが唯一のワンホーン盤だ。パーランの黒っぽいドスの効いたピアノが効果的だが、曲調は全体的に都会的な感じでアーシーな感じはしない。前後作と比べてもなぜお蔵入りしたのかわからないような良い感じの一枚だ。(しげどん)
HERE 'TIS / Lou Donaldson
Lou Donaldson(as), Baby Face Willette(org), Grant Green(gr), Dave Bailey(ds)
オルガン入りのリーダー盤はこれが初。以後、オルガンが多用される。
ジミー・スミスのオルガンとはここまでも多数共演してきたが、オルガン入りのリーダー盤はこれが初めて。ここからオルガン多用時代が始まり、ルウドナ盤=オルガン+ギター+コンガのようなイメージが定着する。この盤のオルガンは、ベイビー・フェイス・ウィレットだ。ギターはグラント・グリーンが参加している。この手の音は、アメリカでは受け入れられたが、日本では人気がなく、80~90年代にクラブ系の人気で復権することとなる。それにしても、オルガンという楽器は電気楽器ということもあり、ピアノと違い鍵盤を押している間は音が鳴り続けるという特性から、盤のカラーを圧倒的に支配してしまう気がする。リーダーのルウドナも吹いていない時は母屋を乗っ取られている感じだ。オルガンとギターだけで楽しそうにグルーヴしている場面もある。(hand)
はじめてのリーダー作としてのオルガンのワンホーン・カルテットである。グラント・グリーンのギターで、オルガンはベビー・ファイス・ウィレットというメンバーなので、コテコテの黒っぽいソウル感あふれる演奏をイメージしがちだが、ガーシュインの有名曲A Foggy Dayではじまる一曲目の意外な感じや、ほかはブルースが多いもののパーカーのCool Bluesも、曲調は都会的な感じで、全体的に泥臭いブルース感覚はない。でもオルガンの存在感が強く、ギターもわりと前面に出ているので、ルウドナさんはいつもどおり吹いているのだが、彼の存在感がやや薄くかんじてしまう。(しげどん)
GRAVY TRAIN / Lou Donaldson
Lou Donaldson(as), Herman Foster(p), Ben Tucker(b), Dave Bailey(ds), Alec Dorsey(conga)
ハーマン・フォスターのピアノが一旦戻ったワンホーン盤
オルガン盤が続くのかと思うと、ハーマン・フォスターのピアノ入り盤になる。タイトルの意味は、ぼろ儲けできる仕事、らしい。お気楽な感じのバレットのコンガがよく鳴っていて、ピアノよりオルガンが合っているようにも思える。タイトル曲①は、ケニー・バレルの「ミッドナイト・ブルー」を思い出す雰囲気。バレットが共通だ。「ミッドナイト・サン」に入っていたキャンディがまた入っているが、「ミッドナイト・サン」は未発盤なので、その辺は仕方ないのだろう。こちらが初出盤なのだった。(hand)
タイトル曲はブルースだが、全体的にはスタンダードなウタモノを素材にしている。あまりコテコテにアーシーな感じはしないので、良い感じだと思う。ルウドナさんはパーカーを知る前はジョニー・ホッジスをアイドルにしていたというから、古いスタンダードに愛着があるのかも。ポルカ・ドッツ・・・などはコンガ抜きで良い感じだと思うが、盤全体としてはもっとソウルフルなほうがまとまりはあったのかもしれない。私はあくまでもウタモノをうまく演奏するジョニー・ホッジスを求めたルウーさんが好きだけど。(しげどん)
A MAN WITH A HORN / Lou Donaldson
Lou Donaldson(as), Grant Green(gr)
1,3,5,7,9:Brother Jack McDuff(org), Joe Dukes(ds)
2,4,6,8:Irvin Stokes(tp), Big John Patton(org), Ben Dixon(ds)
1961年と63年の録音を交互に収録した発掘盤。グラント・グリーンが参加
1999年に発売された61年と63年の録音を交互に収録した発掘盤。ムーディな①ミスティから始まる。63年はアービン・ストークス?という知らないトランペット入り。全曲オルガン入りで61年の①③⑤⑦⑨はジャック・マグダフ、63年の②④⑥⑧はジョン・パットン。聞き分けは難しいがオルガンジャズのトレーニングにはなる(笑)。グラント・グリーンは両方とも入っている。61年がバラードばかりなので、ミドルテンポ以上の63年と交互に収録したのかもしれない。(hand)
・新宿ジャズ談義の会 :ルー・ドナルドソン CDレビュー 目次
・Lou Donaldson CDリーダー作 ①・・・このページ