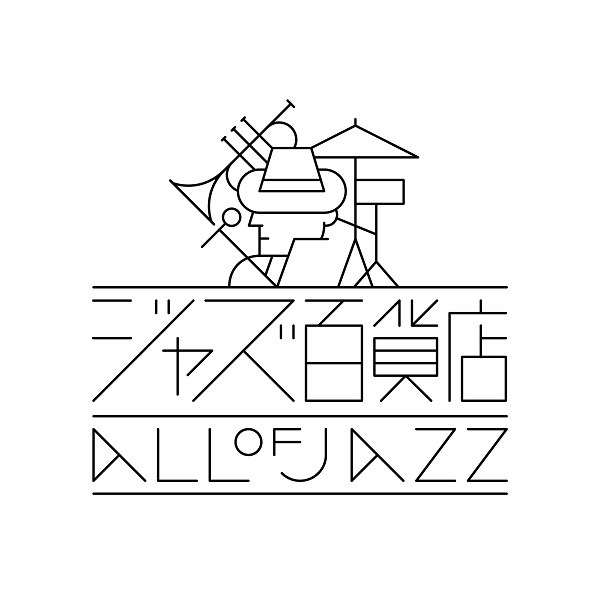Eric Dolphy エリック・ドルフィー サイド作③
ドルフィーが最もフリーに近づいた時期かもしれません。オーネット・コールマンの問題作「フリー・ジャズ」に参加したのもこの時期です。オリバー・ネルソンの歴史的名盤「ブルースの真実」にも参加しています。ジョージ・ラッセルの「エズセティックス」も必聴です。(しげどん)
・新宿ジャズ談義の会 :エリック・ドルフィー CDレビュー 目次
JAZZ ABSTRACTIONS / John Lewis
Gunther Schuller(arr,cond), Jim Hall(gr), Ornette Coleman(as:1,4), Eric Dolphy(as,b-cl,fl:3,4), Robert DiDomenica(fl:3,4), Bill Evans(p:3,4), Eddie Costa(vib:3,4), Charles Libove, Roland Vamos(vln), Alfred Brown(viola:2), Harry Zaratzian(viola), Joseph Tekula(cello), Alvin Brehm(b:1), George Duvivier(b:3,4), Scott LaFaro(b), Sticks Evans(ds:1,3,4)
ジョン・ルイスの共演の第3作のアブストラクト(フリー)な1曲目にはドルフィーはいない。
ドルフィーとジョン・ルイスの共演の第3作。改めて聞いたところ、意外に良かった。オーネットの「フリー・ジャズ」が今聞くとそれほどフリーと感じないのに比べ、この盤の冒頭タイトル曲①はそのオーネットが参加し、かなりフリーな感じがする。②以降の曲は、それほどフリー(アブストラクト)な感じはしない。残念ながらドルフィーの参加は③以降で、③④⑤のジャンゴのように知ったメロディは、バリエーションとして楽しめるが、ドルフィーはフルートのみだ。⑥〜⑨はオーネットとドルフィーの共演だが、オーネットがアルトだけなのに、ドルフィーは3楽器とも吹いているのでバトルにはなっていない。ジョン・ルイス自身は総監督でピアノは弾いていない。(hand)
FREE JAZZ / Ornette Coleman
Left channel:Ornette Coleman(as), Don Cherry(pocket tp), Scott LaFaro(b), Billy Higgins(ds)
Right channel:Eric Dolphy(b-cl), Freddie Hubbard(tp), Charlie Haden(b), Ed Blackwell(ds)
オーネットの世紀の問題作の片側はドルフィー
オーネットのダブル・カルテット(左のオーネットのカルテットと右のドルフィーのカルテット)が左右に分かれてフリーを演奏した有名盤で世紀の問題作。ステレオ時代なので有効となった形態だ。その後のフリーと言われる盤に比べるとフリー度は低く聞きやすい。左右のカルテットは勝手な演奏をしている感じだが、リズムが安定しているので、オーソドックスなジャズからそれほど逸脱してはいないと感じる。ドルフィーは活躍はしているが、この感じはオーネットのもので、ドルフィーのリーダー盤との繋がりは感じない。全1曲のフリー・ジャズという曲のメロ自体に魅力を感じないのが愛聴盤にならない最大の理由ではないかと思う。(hand)
THE LATIN JAZZ QUINTET
Eric Dolphy(fl.b-cl.sax), Felipe Díaz(vib), Arthur Jenkins(p), Bobby Rodríges(b), Tommy Lopez(conga), Luis Ramírez(timbales)
もう一つのラテン・ジャズ・クインテットにも参加
同名のLJQだが「カリべ」とは違うメンバーの別バンド。いずれもドルフィーは伸びやかなソロを聞かせているが、やはりドルフィーとラテンの相性は今ひとつだと思う。ただ、「カリべ」に比べてバンド演奏の緊張感はやや高いように感じる。(hand)
STRAIGHT AHEAD / Abbey Loncoln
Abbey Lincoln(vo), Booker Little(tp), Julian Priester(tb), Eric Dolphy(as,b-cl,fl,piccolo), Walter Benton, Coleman Hawkins(ts), Mal Waldron(p), Art Davis(b), Max Roach(ds), Roger Sanders, Robert Whitley(conga)
アビー・リンカーンのメッセージ性の強い盤
アビー・リンカーンがいわゆるラブ・ソングを歌うジャズ・ボーカルからメッセージ性の強い歌の歌い手へと舵を切った盤だと思う。リンカーンの粘り気の強いボーカルはあまり得意ではなくあまり聞いてこなかった盤なので、今回、ドルフィーを聞こうと思って聞いたがあまり聞こえなかった。大御所ホーキンスが目立っている。(hand)
THE BLUES AND THE ABSTRACT TRUTH ブルースの真実/ Oliver Nelson
Freddie Hubbard(tp), Eric Dolphy(as,fl), Oliver Nelson(ts,as), George Barrow(bs), Bill Evans(p), Paul Chambers(b), Roy Haynes(ds)
オリバー・ネルソンの歴史的名盤
20歳でジャズを聞き始めた頃から愛聴している名盤。初心者には難解なドルフィーがすっと理解しやすい不思議な盤だ。批判されているネルソン自身の単調なプレイがいいのかもしれない。エバンス目当てで買ったこの盤がエバンス以外にも視界を広げてくれたと思う。兎にも角にも①ストールン・モーメンツ、は名曲の名演だ。②ホウ・ダウン、だけが盤の雰囲気に合わないと今でも思う。マイルスの名盤「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」のアー・リュー・チャ、と同じだ。(hand)
STRAIGHT AHEAD / Oliver Nelson
Oliver Nelson(as,ts,cl), Eric Dolphy(as,b-cl,fl), Richard Wyands(p), George Duvivier(b), Roy Haynes(ds)
ネルソン&ドルフィーのストレートアヘッド盤
ネルソン盤のサイド参加から双頭名義となったドルフィー。ネルソンの超名盤「ブルースの真実」からわずか6日後の録音。ドルフィーも参加した「真実」直後にドルフィーと双頭で別レーベルに吹き込んだ意味は何か?「真実」がかなりきっかりとアレンジされた内容だったのに対し、こちらはピアノトリオをバックにドルフィーとネルソンが左右に分かれ、思い思いにアドリブを繰り広げるという内容で、あまりサックスが上手いと言われていないネルソンとしては挑戦的な内容と思うが、名盤「真実」の時よりもネルソンのサックス自身の出来や調子はいいと思う。ドルフィーはのびのびと吹いている。(hand)
OUT FRONT / Booker Little
Booker Little(tp), Julian Priester(tb), Eric Dolphy(as,b-cl,fl), Don Friedman(p), Art Davis, Ron Carter(b), Max Roach(ds,timpani,vib)
盟友リトルのリーダー盤にゲスト的に参加
ドルフィー=リトル5のブッカー・リトルをリーダーに、トロンボーンのジュリアン・プリースターを加えた盤。ドルフィーの参加は双頭的ではなくゲスト的。演奏も曲も悪くはないが、キラーチューンがなく、また聞きたいとはなかなか思わない感じがする。(hand)
PLENTY OF HORN / Ted Curson
Ted Curson(tp), Eric Dolphy(fl:3,7), Bill Barron(ts), Kenny Drew(p), Jimmy Garrison(b), Pete La Roca, Dannie Richmond, Roy Haynes(ds)
ミンガスでの同僚、テッド・カーソン盤に参加
ミンガスでの同僚、テッド・カーソンの盤に9曲中③⑦の2曲のみにフルートで参加している。カーソンのバラード演奏にオブリガード的なバッキングをつけるだけでソロはない。しかも、オールド・タウンという超マイナーレーベルのためあまり売れなかったと想像する。ドルフィーをもっと活用していれば、後世にドルフィー人気でもっと売れた可能性はあったと思う。(hand)
EZZ-THETICS/ George Russell
George Russell(p,arr), Don Ellis(tp), Dave Baker(tb), Eric Dolphy(as,b-cl), Steve Swallow(b), Joe Hunt(ds)
難解なジョージ・ラッセル盤の中で最も理解しやすく、聴きやすい名盤
難解な作品の多いジョージ・ラッセルの盤。多分、ラッセル盤の中では最も理解しやすく、しかも名盤度が高いのがこの盤だと思う。小編成で一人ずつが際立ち、中でもドルフィーが破綻しない範囲で、しかもドルフィーらしいソロを吹いている。⑥ラウンド・ミッドナイト、は名曲の名演。(hand)
・新宿ジャズ談義の会 :エリック・ドルフィー CDレビュー 目次