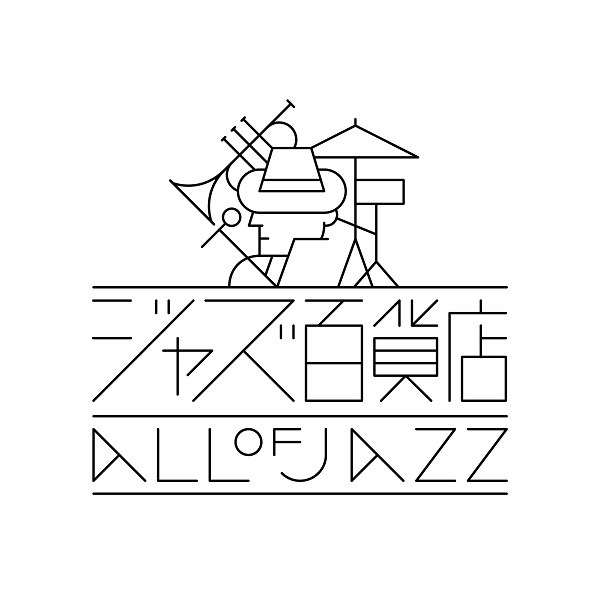Donald Byrd ドナルド・バード リーダー作④ 1963~1971年
1963年のゴスペルコーラスから始まり、64~67年はアルトのソニー・レッドとの双頭バンドを経て、69年には遂にエレクトリック時代に突入していく時期です。(しげどん)
ブルーノートのジャズ黄金期を過ぎ、バードはゴスペル的なコーラスを導入した盤を3枚発表する。そして、ソニー・レッドとの双頭バンドで再びジャズ度が高い三部作+1枚を発表する。レッドの活躍で私としてはバードのジャズとしての第二の黄金期を迎えたと言っていいと思う。その後、エレクトリックに突入してしまう。(hand)
・新宿ジャズ談義の会 :ドナルド バード CDレビュー 目次
A NEW PERSPECTIVE / Donald Byrd
Donald Byrd(tp), Hank Mobley(ts), Herbie Hancock(p), Kenny Burrell(gr), Donald Best(vib,vo), Butch Warren(b), Lex Humphries(ds), Duke Pearson(arr), Coleridge-Taylor Perkinson(choir direction), Unidentified Vocalists(4 men,4women)
ゴスペルコーラスが導入されスピリチュアルな内容のバード自身のフェイバリット盤
ゴスペルコーラスが導入され、またまた雰囲気は一変する。スピリチュアルな内容の現代の讃美歌が作りたかったようだ。バード自身のフェイバリット盤らしいが、全曲にコーラスがほぼ全面的に入っているので、これが苦手だとつらい。バード、モブレー、ケニー・バレル、ハンコックとソロが良く、ウォーレン、ハンフリーズのリズムもピッタリはまっている。バード、モブレーとハンコックは結果的にここから2ヶ月で5枚の共演盤を残すことになる(実質的には各人1回ずつのセッションだがモブレー盤が3枚に分散収録された。)。(hand)
UP WITH DONALD BYRD / Donald Byrd
Donald Byrd(tp, arr & cond:7,9), Jimmy Heath(ts:2–5), Stanley Turrentine(ts:7,8), Herbie Hancock(p, arr & cond:⑧) Kenny Burrell(gr:1–8), Bob Cranshaw(b:1–6), Ron Carter(b:7–9) Grady Tate(ds), Candido Camero(perc7,8) The Donald Byrd Singers(vo), Claus Ogerman(arr & cond:1-6)
唯一のヴァーブ盤はハンコック曲ブラインド・マンやカンタロープ・アイランドをポップに演奏
バードが参加したハンコック盤「マイ・ポイント・オブ・ヴュー」の冒頭に入ったハンコック曲にコーラスを入れた①ブラインド・マンから始まる。前年ではあるが2年近く前のリーダー盤「ニュー・パースペクティブ」でコーラスが入って驚いたが、その時は雰囲気は従来のジャズのままだったので受け入れやすかった。今回は、雰囲気自体がポップになり、コーラスのゴスペル的な宗教性はかなり薄らいだ。黒っぽいセルメンのような感じがする。ブルーノートではなく、唯一のヴァーブ盤だからできた内容かもしれない。好きな人にはたまらない内容かもしれない。特にハンコックの⑤カンタロープ・アイランドはオリジナルとは別のポップな楽しさがある。(hand)
I'M TRYIN' TO GET HOME / Donald Byrd
Donald Byrd(tp,flh), Joe Ferrante, Jimmy Owens, Ernie Royal, Clark Terry, Snooky Young(tp), Jimmy Cleveland, Henry Coker, J.J. Johnson, Benny Powell(tb), Jim Buffington, Bob Northern(french horn), Don Butterfield(tuba), Stanley Turrentine(ts), Herbie Hancock(p), Freddie Roach(org), Grant Green(gr), Bob Cranshaw(b), Grady Tate(ds), Duke Pearson(arr), Coleridge Perkinson(dir,cond), Unidentified musicians(perc), Unidentified chorus(vo)
ブルーノートでのポップなコーラス入りの盤
コーラスは同じブルーノートの前々作「ニュー・パースペクティブ」で取り入れ、ヴァーブからの前作「アップ・ウィズ」でのコーラスにポップな色合いを持たせたバードは、遂に本家本丸のBNにもこのポップ路線を取り入れた。「アップ・ウィズ」とほぼ同時期の録音なので当然の帰結なのかもしれないが、「アップ・ウィズ」がハンコックの人気曲を入れるなど売れ線狙いなのに対し、こちらはやや編成を大きくして、新しさを追及しているように感じる。多少のトランペットやテナーのソロはあるものの、バードのトランペットによるテーマはなく、コーラスと大編成のアンサンブルを楽しむものとなり、私の考えるジャズというカテを超えつつある。バードのプロデューサー色が急に濃くなったと言える。ところで、このタイトル、直訳すると、日本のマイ・ホームたる“家が欲しい”のようになるが、そうではなく精神世界的な意味の“家が欲しい”のだと想像するが、どうなのだろう。(hand)
MUSTANG! / Donald Byrd
Donald Byrd(tp), McCoy Tyner(p), Walter Booker(b),
1-6:Sonny Red(as), Hank Mobley(ts), Freddie Waits(ds)
7,8:Jimmy Heath(ts), Joe Chambers(ds)
ソニー・レッドとの双頭三部作の第1作
アルトのソニー・レッドとの三部作と言われる作品の1作目。モブレーを含む3管でのジャズロック的な演奏もある。「アイム・トライン・トゥ・ゲット・ホーム」以来、1年半ぶりのリーダー盤。コーラス入りの盤が3枚続いたが、今回はコーラスなしで、時代的に8ビートは入るが、久しぶりのストレートアヘッドなジャズ盤。ピアノにコルトレーン退団後のマッコイ・タイナーを迎えた効果が大きく、タイナーがモーダルになり過ぎずいい感じのプレイをしている。バードは時代とともにプロデューサーとしての色合いが強まる人だが、この盤ではまだ純粋なプレイヤーに踏み止まっている。タイトル曲①などは8ビートではあるが、マッコイがコルトレーンバンドよりはずっと軽やかで、マッコイのおかげかポップなジャズロックにはならず、新主流派的な8ビートになっている。作者のソニー・レッドのアルトがバード以上に活躍している。エリントン曲③アイ・ゴット・イット・バッド、はバードのワンホーンが素晴らしい。バード曲④ディキシー・リー、はハンコック風なジャズロック曲。⑤オン・ザ・トレイルも知られざる名演。⑥でモブレーのを快調なソロが聞かれる。おまけ2曲⑦⑧は2年前のコーラス入り盤を録音していた時期のセッションだがストレートなジャズだ。テナーがモブレーではなくジミー・ヒース。ヒース作⑦ジンジャーブレッドボーイはマイルスより2年前の演奏で貴重だ。ヒースが珍しくワイルドでカッコいい。⑥⑧は同じ曲なのでモブレーとヒースの聞き比べができる。バードは2年前がブリリアントだ。オマケ曲は、盤の雰囲気を混乱させることが多いが、この盤では盤の価値向上につながっていると思う。(hand)
ジャズロック路線がかなり明確になった盤。スタンダードも演じているし、やや新主流派的な部分もあるが、AB両面の冒頭曲がジャズロック路線なので特にそのような印象が強い。まるでソプラノのようなソニー・レッドのアルトの存在感が強く、冒頭の曲も彼のオリジナルだ。モブレーが参加しているのだが、彼の印象が薄いのが残念だ。(しげどん)
やや単調なブルースのリフレインが多く、聴きどころがハッキリしない。また激しいドラムがドスンドスンと響き、テナー、トランペットのブローも勢いはあるが、バタバタとした印象で、落ち着いて聞き辛い。(ショーン)
BLACKJACK / Donald Byrd
Donald Byrd(tp), Sonny Red(as),
1-6:Hank Mobley(ts), Cedar Walton(p), Walter Booker(b), Billy Higgins(ds)
7:Jimmy Heath(ts), Herbie Hancock(p), Eddie Khan(b), Albert Heath(ds)
バードのジャズ第二黄金期とも言えるソニー・レッドとの双頭第2作
バードとソニー・レッドとの三部作の2作目。この三部作は、バードのジャズとしての第二の黄金期と考える(もちろん「フュエゴ」前後が第一の黄金期だ。)。いずれも素晴らしいが、本作が一頭地を抜いているのではないかと思う。1作目「ムスタング」とメンバーはほぼ変わらず、ピアノがマッコイからシダー・ウォルトンに変わっただけで、盤の雰囲気は大きく変わっている。ジャズロック度がより強まっているが、盤はとても良くできている。また、前盤から引き続き。レッドの活躍が光る。ドルフィ的なニュアンスもあるカッコいいアルトだ。レッドにとってもこの三部作がピークの記録かもしれない。シダーもいいが、モブレーもまずまずだと思う。バード作のタイトル曲①はクイーンのウィ・ウィル・ロック・ユーを思い出すリズム、②③ともにバード版セブン・ステップスのような曲、バードの教え子作④エルドラドはバード版ソーホワット、⑤ベールストリートはバード版サイドワインダー、というように全体にキャッチーな仕上がりで飽きさせない。米盤CD収録のオマケ曲⑦オール・メンバーズは、三部作の3年前に既にレッドと共演していた記録だが2人はデトロイト時代の同級生のようだ。(hand)
冒頭曲ではジャズロック路線が継続されており、この当時の売れ線路線だ。一方でエルドラドのようなモーダルな演奏もいい味を出している。ソニー・レッドのいがらっぽいアルトはモブレー以上に目立っている。オリジナルも3曲あり、盤全体に存在感を及ぼしている。(しげどん)
3管の迫力を感じられるアルバム。ビリー・ヒギンズのドラムが重厚で重いので、スピード感のある重戦車の様なハードバップだ。ノリ良く身体の芯に響く、なかなか心地良く陶酔が出来そうなアルバムである。(ショーン)
SLOW DRAG / Donald Byrd
Donald Byrd(tp), Sonny Red(as), Cedar Walton(p), Walter Booker(b), Billy Higgins(ds,vo)
ソニー・レッドとの双頭三部作の第3作
バードとソニー・レッドとの三部作の3作目。メンバーは、モブレーが抜けただけの違いだ。レッドとは、未発盤「クリーパー」まで共演している。録音順としてはサム・リヴァース盤の次となり、これに比べるとレッドもかなりオーソドックスに聞こえ、タイトル曲①も8ビートながら落ち着いたジャズに聞こえる。ドラッグはゆっくり効く麻薬かと思ったがスペルが違いゆったりしたダンスのことのようだ。ヒギンズのボーカルと表示されてはいるが、聞かれるのは後のラップにつながる合いの手のようなボイスが少量だ。シダーとウォルター・ブッカー共作③ブックス・ボサ、はブルー・ボサを明るくした感じ。レッド作④ジェリー・ロール、はサイドワインダーのそっくり曲。シダーとロニー・マシューズの共作⑤ザ・ローナー、はシダーの活躍が目立つち、盤自体がシダーの隠れ名盤かもしれない。②⑥に久々にスタンダードが入っている。レッドとの三部作は、ジャケだけ見ると、ブラックファンク盤と勘違いしそうだが、中身はストレートなジャズでバードがエレクトリックやファンクに向かう前の純ジャズ時代の最後のピークを捉えていると思う。(hand)
ソニー・レッドとの三作目。タイトルナンバーではビリー・ヒギンスの歌ではなく言葉通りのボーカル=声だ。ファンキーなイメージは薄くなり、電子楽器は入っていないが、後年のフージョン的な軽いさわやかな感じの音で、BGM的に聴き流してしまいそうな音楽だ。(しげどん)
THE CREEPER / Donald Byrd
Donald Byrd(tp), Sonny Red(as), Pepper Adams(bs), Chick Corea(p), Miroslav Vitouš(b), Mickey Roker(ds)
ソニー・レッドとの双頭作の未発盤。チックとビトウスが参加
バード=レッド双頭バンドの81年公表の未発盤。過去にコンビを組んでいたペッパー・アダムスも参加している。リズム隊が、チック・コリア、ミロスラフ・ヴィトウス、ミッキー・ローカーというフレッシュな顔ぶれになって存在感を増している。チック作の①サンバ・ヤントラ、が特に個性的で盤の雰囲気を変えていて、他の曲には従来の流れも感じるが、リズム隊の変更とアダムスの参加で三部作とは趣の違う盤になっている。カスクーナの編集なので当初は冒頭に置かれるはずだったと思われるレッド作のタイトル曲④がB面頭になってしまったと想像する。コリア曲を前にしたほうが売れるという考えだと思うが、レッドのアルトの暴れ度が下がってしまったように感じる。 バードのトランペットが比較的よく鳴っているだけに、CD帯の“バード最後のピュア・ジャズ作品”というコピーが私には悲しく感じる。(hand)
FANCY FREE / Donald Byrd
Donald Byrd(tp), Julian Priester(tb), Frank Foster(ts,ss), Jerry Dodgion(fl:1,3), Lew Tabackin(fl:2,4), Duke Pearson(el-p), Jimmy Ponder(gr), Roland Wilson(el-b), Joe Chambers(ds:2,4), Leo Morris(ds:1,3), Nat Bettis, John H. Robinson Jr.(perc)
バードのエレクトリック宣言盤
リーダー、サイド盤ともに、68年は録音がなく、2年ぶりのリーダー盤。バードの音楽は大きく変化する。いきなりの8ビートでエレピ、よく聞くとベースもエレベだ。そして鳴るのはトランペットではなく、メローなフルート。何かに似ている、そうだチックの大ヒット盤「RTF」だ。前作「ザ・クリーパー」に参加していたチックはバードの周辺にいたはずなので、ヒントを得た可能性は高いと思う。ギターやパーカッションもRTFは取り入れていく。唯一の疑問は、なぜバードよりも先輩格のフランク・フォスターを使ったのかだ。バッパーやコルトレーン・スタイルを避けたかったのだろうか。その意味では正解なのかもしれないが、もう少し軽い感じが合うとは思う。この時期からバードのサイド参加は激減する。(hand)
KOFI / Donald Byrd
Donald Byrd(tp), Bill Campbell(tb:1), Frank Foster(ts), Lew Tabackin(ts,fl:1,2), Wally Richardson(gr:3-5), Duke Pearson(el-p), Ron Carter(b), Bob Cranshaw(el-b:2), Mickey Roker(ds:3-5), Airto Moreira(ds:1,2,perc:3-5), Dom Um Romão(perc:3-5)
発掘盤ながらマイルスを感じる好内容の盤
69,70年の録音だが95年発表の発掘盤。2回のセッションの間に「エレクトリック・バード」が録音されている。70年頃からプロデューサー化していくバードだが、この未発盤では結構思い切り吹いていて好ましい。ライブ感のある盤だ。タイトル曲①コフィ、はルー・タバキンのフルートが印象に残るモーダルなカッコいい曲。このおかげで盤の価値が高まっていると思う。ピアソンのエレピもいい雰囲気を出している。③パーペチュアル・ラブ、④エルミナ、はモロにマイルスの影響を感じる演奏だ。オマケ⑤ラウド・マイノリティ、はフランク・フォスターの曲で、本人が活躍する。「ファンシー・フリー」では、なぜ今フォスター?と思ったが、十分に状況に適合していると思う。マイルスを感じ過ぎて未発表?というくらいマイルスを感じる盤だ。(hand)
ELECTRIC BYRD / Donald Byrd
Donald Byrd(tp), Bill Campbell(tb), Jerry Dodgion(as,ss,fl), Frank Foster(ts,a-cl), Lew Tabackin(ts,fl), Pepper Adams(bs,cl), Hermeto Pascoal(fl:3), Wally Richardson(gr), Duke Pearson(el-p), Ron Carter(b), Mickey Roker(ds), Airto Moreira(perc)
ブラックファンクに至る直前のエレクトリック・ジャズ
前作「ファンシー・フリー」でエレクトリックを大胆に取り入れたバードがまさにそのまんまのタイトルの盤を作った。同じエレクトリックながら盤のカラーを決定付けているのがワウワウのようなギターで、前作のエレピとは違う雰囲気だ。マイルスがエレピ中心の「イン・ア・サイレント・ウェイ」からその後最終的なアガパンではキイボードなしのギター中心となったのを先取りしたような感じかもしれない。この前月、マイルスは東西フィルモアでライブをしており、バードも聞いたのかもしれない。この盤は、今回、初めて聞いたが,想像していたブラックファンクではなく、ザビヌル的なのどかさもあるエレクトリック・ジャズだ。アイアート作③ジババ、はエルメット・パスコアルも参加した本格的なブラジリアン・エレクトリックジャズ。ラスト④ザ・デュード、だけは多少ブラックファンクを感じた。(hand)
ETHIOPIAN KNIGHTS / Donald Byrd
Donald Byrd(tp), Thurman Green(tb), Harold Land(ts), Bobby Hutcherson(vib), Joe Sample(org), Bill Henderson III(el-p), Don Peake(gr), Greg Poree(gr:1,2), David T. Walker(gr:3), Wilton Felder(el-b), Ed Greene(ds), Bobbye Porter Hall(congas,tambourine)
クルセイダーズのメンバーの参加で?フュージョンの香りのする盤に
ベースとギターの絡んだリズムがフュージョンを感じさせる盤だ。メンバーを見ると、ジョー・サンプル、ウィルトン・フェルダーというクルセイダーズのメンバーが参加している。クルセイダーズはこの71年にジャズ・クルセイダーズからクルセイダーズに名前を変え、フュージョン化している。そのきっかけがこの盤だったのかもしれないが、クルセイダーズ初盤「パス・ザ・プレート」が71年5月発売なので、逆にバードがフュージョン的な2人を活用した可能性がある。ハロルド・ランドとボビー・ハッチャーソンは、60年代の新主流派的な傾向をこの後更に推し進めるていくことになるが、この時点ではフュージョン的なサウンドに貢献している。バードのトランペット自体は、ファンク的なリズムに乗って気持ち良さそうに吹いているが、そのプレイそのものにはあまり魅力を感じなかった。トータルなグルーヴを楽しむ音楽なのだろう。ソロイストはいいが、リズム隊は15分も同じことをやっていて楽しいのか、正直、あまり理解できない。(hand)
・新宿ジャズ談義の会 :ドナルド バード CDレビュー 目次